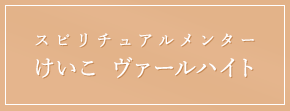2021年9月8日
自分が自分の中心に居続けると何が起きるのか
今日、ロサンゼルスでやっている、ゴッホのエキシビションに行きました。
これは通常の絵画展とは違って、ゴッホの絵を壁面四面に映像として連ねて流していく、それ自体がとても芸術的な映像作品のようなものでした。
私はゴッホは好きでも嫌いでもないのですが、友人がゴッホが大好きだということで、連れられて行った。
そして、エキシビション会場に一歩入った途端に、そこはかとない哀しみがそこら一帯に漂うのを感じました。
それを感じた時、やはり「ああ、ゴッホの絵は哀しみがあるんだよなあ」と思った。
そして、だからこそ後世の一部の人たちが熱狂的に愛し、そしてこのようなエキシビションが創られ世界中を回るのだと思った。
またもう一つ、絵を見ていて強く感じたのは、ゴッホのオリジナリティについて。
彼は愚直なまでに「ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ」であり、それ以上でも以下でもあれなかった。
ただ、あそこまで自分をさらけだして、さらに何者にも媚びることができず、誰かや何かのために自分を曲げることができなかったゴッホ。
その時代、そうであることは、芸術家にとっては実はとても難しくて、なぜなら、サロンや一般の評価、またパトロンを得ていくために時代に擦り寄らなくてはならなかったであろうし、それができなかったからこそ、彼の絵は生きている時にまったく売れなかった。
絵を見ていて、ただゴッホの
「これの何が悪いんだ!これの何がいけないんだ!」
という叫びが聞こえていました。
筆先の跡の一つ一つに、ゴッホのこの叫びがこだまして聞こえて、これしか描けなかったゴッホ、愚直なまでに自分の絵にこだわったゴッホの哀しみと憤りをやはり感じたのです。
何を言いたいのかというと。
単純に、ゴッホは自分の中心にしかいられない人だったんだなあということ。
単純に、周りに合わせたりフレキシブルに自分の才能を折り曲げつつうまく表現することができない人だったんだと思った。
そして、今のアセンションが進む地球においては、みなゴッホの生き方に憧れるかのように、彼の絵をもてはやす。
それはやはり、自分の中心にいられない人ばかりの昨今、彼の生き方は賞賛を得るに値するのだと。
そしてここからがようやく本題なのですが、人が自分の中心にしっかりといられるようになったとき、何が起きるのか。
それは、改革です。
革命とも言える。
これまでは、自分はただ人から影響されたり、人によって翻弄されるだけの人間だった。
しかし、自分が自分の中心にいられるようになった途端に、全てが変わる。
自分が司り主になる。
他者に与える影響もそうだし、他者に揺り動かされるのではなく、自分が他者を揺り動かすようにもなる。
その結果起きてくるのは、その人が欲しくてやまなかった状況です。
すなわち、人生を自らクリエイトしていく力を持つということ。
そして、ゴッホ展によって、なぜこれを改めてしみじみと感じたのかというと。
ゴッホは、なぜ死んだ後、爆発的に売れたのか。
結局それは、彼が自分の中心に居続けたから。
でも、じゃあなぜ死ぬ前には売れなかったのか。
それはやはり、当時の時代背景が色濃かったと思いますし、結局はサロンでパトロンに気に入られたり世間の風潮が求めているものに擦り寄ることができたとき、初めて「絵として見てもらえる」「評価される」という図式が現れただろうから。
単純に作品の素晴らしさや愚直なまでに真っ直ぐなエネルギーだけでは売れなかった時代背景があったから、ということになりますが。
しかし、今の時代は、ただ、実力だけ、ただ作品だけ、そしそれがありのままのその人本人を表している、一切ブレずに。
その状況が、いつまでも世間の人たちを魅了してやまない状況となって、ゴッホの不器用な人柄と共に認められ、世界的爆発的ヒットを生み出している。
そのように感じたのです。
自分の中心に居続けることは、あるがままの自分を認めること。
たとえそれがおかしかったとしても。
他者と合わなすぎたとしても。
その時初めて、すべて自分中心となって世界は動き始めます。
徹底的に自分で居続けること。
反省も他者の真似もいらない。
すごく簡単なようで難しい、でも、誰でもできなくない。
そこを目指しましょう。
それでは、本日も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
▼▼▼スポンサードリンク▼▼▼
▼▼▼スポンサードリンク▼▼▼

いいね!しよう